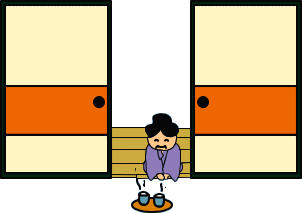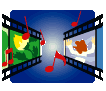
ローカルな子どもの頃の思い出 (回想録)主に昭和20年代
半世紀以前、テレビの無い時代、まだ娯楽と言えば、真空管ラジオ、手回し蓄音機、映画、紙芝居、バクダン、盆や正月、ただ唯一の芝居劇場(同級生の西村君のお父さんの経営)、祭り、海や、山、川で遊ぶ事。魚釣りや、釘たて、缶蹴り、コマ回し、ビー玉(無い場合は、当時交通標識が、今のようになる時、木の板に打ち込んであった、ビー玉の大きなガラスで反射するようになっていた、球ガラスを取り出してビー玉を作ったり、不用になったレンガを砕いて丸い玉を作って)、面子、竹筒テッポウ、割り箸ピストル、パチンコ(股木にゴムを付け、小石などを飛ばす飛び道)、自分達で手作りしたもので遊んでいました。
電燈が2個程度だったのが、電気がメーターに変わり、各部屋に電気の灯が灯ったのが、昭和25年ごろだったと憶えています。電球の球がしばしば切れ、近くの電球を販売している家(一般の家;サンシショ?)に買いに行ったことも覚えています。よく停電もありました。一般の家には、まだ電話も無く、昭和31年父の死亡の際、兄が勤め先に連絡するのに、久手郵便局まで行ったといいます。父母が庭に鉄の窯で塩を作っていた、記憶があります。舗装道は、大田の駅前通りだけで、外は、でこぼこ道でした。
自動車は、ほとんど無くて、セルモーターが無く、車の前の穴に鉄棒を突っ込んで回しエンジンがかかる状態でした。木炭車の記憶もあります。多分、小学校に入る前だったと思います。左右の方向指示機は、矢印の様なピョンと出るものでした。本当にアナログの世界だったのです。
大田市になる前、安濃郡と言われていた時代、久手町(昭和12年波根西村と刺鹿村が合併して久手町になる)の駅前は、夏には盆踊りで9月1日から3日間夜遅くまで踊り、賑わっていました。駅長さんや駅員の方々がいて和みのある駅でした。駅長さんの娘さんが同級生で、確か小学6年の頃、お父さんの転勤で同級になったと思っています。
呉服店大田屋の傍の西川踏切には、踏切番のおじさんがいて汽車や往来の人々の安全を守っていた事を思いだします。その向かいには、小さな小さな駄菓子屋おじさんが商いをしていました。
砂利道の駅前の広場には、紅白に巻かれた櫓が立ち、色とりどりの晴れ着?浴衣の着物で着飾った踊り子達が、櫓の上の太鼓や横笛に併せ、歌い手と奏でる盆踊りの歌に併せ、舞い踊っていました。いまの、「おわら風の盆」のよう?でした。 丁度、9月1日からは二学期の最初の日、子ども心に、休みだったら良かったのに思いながら、その日を迎えた思い出があります。明治7年生れの祖母スワばばさんは、白髪でこの盆踊りを楽しみにして、毎年踊っていました。
夏の夜、久手駅前の広場は、野外映画館に早代わり、夏の遅い夕闇が迫る頃から、町の沢山の人々が集まり、映画の上映が始まり、それを観賞に行った思い出があります。まさに、「湯布院の映画祭」のよう?です。今のように、カラーでなく、白黒でしたが、時たま「総天然色」の字幕入りの映画の上映もありました。
神社の石見神楽の奉納舞いや、近くのお寺曹洞宗真光寺さんの法会での説法、お焦げを戴いて美味しかった事も思いでとして残っています。
夏の日照りの田んぼに、父が黒田川の水を脚ブミの水車で水樋に流し、田んぼに水を供給していた事も思い出します。梅雨の時期、ホタルが飛び交う田圃の風景が思い起します。ホタルを捕まえてきて、蚊帳の中に入れ、寝たことも思い起こします。昭和30年代に入るとその光景は無くなりました。刺鹿の曹洞宗円光寺の下を流れる小川で、しじみ貝を取ったり、江谷川をさかのぼり、清滝まで足を延ばした事もありました。
糸電話を作り、中尾の親戚の石田宅と1年上の財間宅とを結んで遊んだ事もありました。50mはあったと思います。
ラジオは、最大の娯楽でありました。松江放送局枕木山からのラジオ番組、夕方、6時前に帰り、連続ドラマ「オテナの搭」、「紅孔雀」、「笛吹き童子」等など聞いていました。並み四のラジオは、ぴーぴー、ガーガーと言い、同調のつまみと、周波数、及び音量のボリュームでした。
朝鮮戦争影響で、道に落ちている釘など金属類や、空き瓶を拾い、港近くの工場にもって行き、一円から五円ほどのお小遣いになりました。50銭銀貨を使った覚えがあります。50銭が廃止された頃、鉄の椀で溶かして遊んだ記憶があります。多分小学2、3年の頃ではなかったかと思います。
小学校1年から5年まで掛戸松島近くに小学校があり、学校に通うのに1時間ぐらいかかっていたと思います。学校の掛戸よりに駐在所があり、同級生の女の子がいました。仮設の小学校で学芸会の時は、校庭側に六年生の教室があり、壁を取り外して、早代わりの講堂?になりました。冬は、各教室に大きな火鉢が一つあり、そこで暖を取って、お昼前には、アルマイトの弁当箱をその火鉢の廻りに置き、昼の食事を皆でしました。たしか、お味噌汁が出ていたと記憶しています。小学校入学時には、杉皮の屋根で入学の記念写真には瓦が積んでありました。校舎は、ロの字で廊下の真ん中に何本かの柱があり、よじ登っていました。裏には、国鉄の山陰本線が走っていました。父母の話によれば、久手小学校は、戦前は県内有数な木造2階建ての立派な校舎があったそうです。残念ながら、火災で焼失し(1946年1月 昭和21年)、跡地には、久手中学校が建てられたとの事です。一年生は、4組。二年以上は3組になっていました。い、ろ、は、に、の組になっていました。
本屋さんや駄菓子屋さんが、駅の近くにあり、しばしばいっていました。子ども達の社交場のようでした。銀行は、山陰合同銀行久手支店のみでした。
久手町役場は、駅から港に通じる道の久手の中心部にたしか三階建てで、搭のあるモダンな役場がありました。搭の上からは、時を告げるサイレンが鳴っていた記憶があります。いつの頃か忘れましたが、搭に登った記憶があります。今、何に使われているのか解りませんが。
スケーターを買ってもらい、でこぼこ道で遊んでいました。そのスケーターが60年後の今、流行している事に驚いています。あ、そうそう、要らなくなった戸車の車を使って、一人乗れる車を作って遊んでもいました。いや、作ってもらったのかなー。
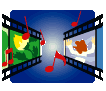
小正月には、竹で組んだ櫓にその正月飾りや、書初めなど燃やし、その年の繁栄を願ったもので、焼きおもちもその時から食べました。いつの頃か、この様な、行事は行われなくなりました。
よく、桑の実を食べ、口の廻りや手を赤くして、叱られたここもありました。秋には、イナゴ取で秋の田圃を歩き回りました。
2月の節分や、3月の大田の彼岸市は、大きな楽しみの一つでした。久手駅から大田駅まで汽車で小学生の1、2年の当時、子ども運賃5円だった事を覚えています。大田で牛の市が起ち、バクロと呼ばれた牛仲買人で賑わっていた。小牛をつれて父と歩いていったことを思い出します。まだ、小学生の頃は、バスも無く、もっぱら国道9号線や、勾配のきつい「いちにわ坂」を越え、市井を抜け大田に歩いて入る事、もしくは、国鉄の列車での移動でした。小学高学年になると自転車ででの移動でしたが。
列車は、SLで、汽笛の大きいこと、あの力強い動輪の響きは、忘れられません。その後、近所の鍛冶屋さんの隣りのサンキチおじいさんが、言っていた事は、大正のころ、久手から大田に抜ける山陰本線の工事に携わり、大変だったと言っていました。{石見大田まで鉄道が開通したのは大正4年、山陰線の全線開通は、昭和6年(1931)「島根県の百年」内藤正中著による}先人達が、苦労して作り上げたものだったのだなーと思い、今の、これからの未来に引き継がなければと思いました。
春から夏には、まだ整備されていなかった大原川は、魚釣りにもってこいの場所でした。家の前(高橋校長宅)のみつるお兄さんや裏のひろしお兄さんと一緒に遊んでもらいました。黒田川でうなぎ取り、田んぼでドジョウ取り、日本海の海での魚釣り、等など思い出します。波根湖干拓の名残で菱(ひし)の実が道路にあり、歩くのが難儀だった事を思い出します。
久手港の防波堤(今の漁協の少し西側から堰堤が伸びていました。)に木造の飛び込み台があり、高学年の生徒たちはよく飛び込みをしていました。
久手港には、木造船の造船所が2軒ありました。新造船の進水式は、それはそれは盛大でした。小学三、四年のころ、夏休み中進水式があり、同級生や友達が港の中に進水したばかりの、船に向かって泳いでいったのを見て、自分も泳いでいってみようと思い、泳ぎ始めたら、突然、深くなっていて、溺れそうになり、無我夢中で手や脚をバタツカセテ、大事にいたらなく浅瀬まで戻った記憶があります。それから、泳げるようになりました。危険な事をしたと思っています。
歴史書によると久手港は、北前舟の寄港地の一つになっていたと記録されています。また、明治の頃には、日本海航路(大阪商船会社;大正11年まで)の寄港地でもあったようです。(「島根県の歴史」 内藤正中著;山川出版社)明治から大正にかけて、人口は、大田より多くかったと記載されています。
裏の西和田山での遊びも、面白く記憶しています。洞窟探検、ターザンごっこ等など、思い出は尽きません。
50年〜60年前、隣り町の鳥井の百済に行く時は、砂が少なく今の4分の1の砂地、汐の退いた時、海水につかりながら通るか、険しい山越して百済の集落に行きました。




追記;町から江谷行く途中、右側にレンガ工場があり、トロッコがありました。夏目漱石の小説「トロッコ」を読んだ時、風景が重なり、無性に懐かしさがこみ上げてきた記憶があります。今の久手交番の少し先の左側に、療養所がありました。鈴見には、瓦工場がありました。
中学の時、兄と一緒に江谷の本和田さんの裏山に登り、岩山城({多胡辰敬−たごときたか−}円光寺の開基、永録5年2月5日毛利に攻められ落城討死=「石東文化資料による杉本雲生作品集」 編集者 宮脇英世(高校の時の担任の先生)、 及び 久手町史部会編=平成4年2月発行より)の城跡か以前の円光寺の跡かどうか、はっきりとは解りませんでしたが少し広いところがあり、石の穴があった記憶があります。
江谷の奥に父が働いていた木材伐採のところに、木馬道があり、お手伝い?と言うより遊びに行った思い出があります。久手駅の国道側には、材木が山のように積まれて、引込み線には、貨物貨車に積荷をして賑わっていました。そういえば、中学生の時、近所の同級生友達と一緒に、近くの製材所で1週間ほど、木の皮むきのアルバイトをし、250円ほどの賃金をいただきました。初めての労働に依る賃金でした。小学生の頃、その製材所の積んである木の上で遊んだりしていました。
大陸からの引き揚げ者で同級生が何人もいたし、一時的に空いていた離れに、時を別々にして、同級生の家族が住んでいました。隣同士だったから、よく遊んでいました。引き揚げの時期、2歳から3歳ぐらいで、大変だった事と思います。