�����E�{������n�k2008.6.14 �l7.2 �k�x�U���A8;13�@�R�Ôg�����@���S�P�R���@�@
|
| �����k�n�������m���n�k�i�ʏ́g�����{��k�Ёh�j2011.03.11 |
| ���{�����@�l9.0�@�@����Ôg�@�@�@�A���n�k�B |
| ���s15,000�`20,000���A10m���̑�Ôg�҈��A�Ђ������B���{�C�a�̍L�͂̊�Ղ��j�f�����Ƃ����B���{�̊ϑ��j��ő�̋���n�k�B�Ôg�̓A�����J��y���[�E�`���ȂNJ����m�ōL���ϑ����ꂽ�B��䕽���т�0.7m���~���A�Ôg�Ƒ��܂��Ċ��������B�����_�ɂ�����A�����{�ň��̍Ж��ƌ�����B���Q�ғ����d��������ꌴ���ŋً}��~��ɗ�p�@�\�}�q�ɂ���āA�����I�ȘF�S�n�Z�����������ƌ����Ă���A���ː��������o�̋��ꂩ�����͂ɔ��w�����o���ꂽ�B�l�ނ����߂Čo�������n�k�E�Ôg�ɂ�錴�q�F�̘F�S�n�Z�����B���̐l�I��Q |
�����E�{������n�k2008.6.14 �l7.2 �k�x�U���A8;13�@�R�Ôg�����@���S�P�R���@�@
|
| ��2003�N�\�����n�k2003.09.26 |
| �k�C���@�l8.0�`8.1(8.3?)�@�s��3�A�������A�Ôg�A�Ζ��^���N����B |
| ���쐼�����͂邩���n�k�i���d�R�����j1998.05.04�@�l7.4�`7.6�i7.5�j |
| ���O���͂邩���n�k1994.12.28 |
| ���k���@�l7.6�`7.7�@���s3�A�X�E����Ŕ�Q�A�Ôg�B |
| ��1994�N�k�C���������n�k1994.10.04 |
| �瓇�i����j�@�l8.2�`8.3�@���s15�i����Ȃǁj�A��Ôg�B |
| ���k�C���쐼���n�k1993.07.12 |
| ���{�E�k�C���@�l7.7�`7.8 |
| ���s230�A��Ôg�i�ō�32m�j�A�������B���C�B�i���V�A�E���N�����j�ł��Ôg��Q�B |
| �����H���n�k1993.01.15 |
| �k�C���@�l7.5�`7.8�@���s2�A��1,000�A�n����A�[���n�k�B�Ôg�B |
| ��1968�N�\�����n�k1968.05.16 |
| ���k���@�l7.9�`8.2�@���s50�]�A�Ôg�B |
| ���`���n�k1960�i���a35�N�j.05.22�@�`���암�@�l9.5 |
| ���s2,200�`5,700�i1���H�j�A�L��n�k�ϓ��A��Ôg�i�ő�24���j�A���E�j��ő�̒�����n�k�B�Ôg�͑����m��`�d���A�n���C�Ŏ�60�B���{�ɂ���K�͉��n�Ôg�i6���j�A���s140�ȏ�B�k����1,000�~200km�ɂ��y�B |
| ���G�g���t�����n�k1958.11.07 |
| ���{�E�瓇�i�𑨁j�@�l8.1�`8.3�@�Ôg�A���{�{�y�L���B |
| ���\�����n�k1952.03.04�@�k�C���@�l8.1�`8.3�@���s30�]�A�Ôg�B |
| ������n�k1948�N6��28���@�l7.1�@����3000�������B1944�N�̓���C�n�k�̗U���n�k |
| ����C�n�k�i���a��C�n�k�j1946(���a21�N).12.21���{�E��C�i�l���j�@�l8.0�`8.2 |
| ���s1,300�`1,400�A�Ôg�B�@�^���N�łU�T�N |
| ���O�͒n�k�i����C�n�k�̗]�k�j1945(���a20�N).1.13�@���m�����S�s�̐�����k���@�l6.8 |
| ���s2,306���A |
| ������C�n�k1944.12.07�A���a�P�X�N�B�@���{�E����C�@���C�n���@�l7.9�`8.1 |
| ���s1,200�ȏ�A�S��2��6130����Ôg�i10m�j�펞���̕K���̂��߁A��サ�炭�ڍוs���B |
| �����a�O���n�k1933.03.03�@���a�W�N�@���k�����i�O���C�݁j�@�l8.1�`8.5(Mw8.4) |
| �i�Ôg�j���s3,100�A��Ôg�i�ő�29m�j |
| ���֓��n�k�^�֓���k��1923.09.01�@�吳�P�Q�N |
| ��֓��@�l7.9 |
| ���s99,000�`142,000�i20���ȏ�H�j�A�S����20�����A�S����20�`40���ˁB�����s�X�قڏĎ��A��Q�z�����̍��Ɨ\�Z�̂R�{�B���l�E���c���E�O���R�ł���Q�r��A�k���Ώo���A��Ôg�i�ő�12m�j���{�j��ň��̍ЊQ�̂P�B |
| �������O���n�k�Ôg���k�����i�O���C�݁j1896.06.15�@�����Q�X�N�@�l7.2�`8.2�iMt8.5�j |
| ���s22,000�A����Ôg�i�ő�38m�j�n�k���y���i�������Ôg�n�k�j ���{�ߊC�̒Ôg�ЊQ�Ƃ��Ă͎j��ő�B |
| �����{�E�k�C���i�������j1894.03.22�@�l8.2�`8.3(?)�Ôg�B |
| ���Z���n�k1891.10.28�@�����Q�S�N�@���E���m���@�l8.0 |
| ���s7,300�A�S����20�����A��f�w�B |
| ���`���k�����n�k1877.05.10�@�`���k�����@�l8.3�`8.5�i9.0?�j |
| �������A��Ôg�A���{��2m�ȏ�����n�Ôg�B1868�N�n�k�̂�����Ŕ������B |
| ���l�c�n�k1872.02.04�i�������Ό��j�@�l7.1�@���ҁE�s���s��550���@�Ôg�����B |
| �������n�k�i�������C�n�k�E������C�n�k�j�P�W�T�S�N�P�Q���Q�R���`�P�Q���Q�S�� |
| ����C�@�l8.4�`8.6�i8.4�~2�j�A���n�k�B |
| ���s����`10,000�i30,000�H�j�L���Q�A��Ôg�i�ő�16m�j���C�n�k����32���Ԍ�ɓ�C�n�k�����B |
| ��1856.08.23�@�X�����@�l7.5�`8.0�@1968�N�\�����n�k�Ɏ����n�k�B����29�A�Ôg�P���B |
| �����k�Œn�k�P�V�X�R�N�Q���P�V���@�l8.0�`8.4�@���s���\�`700�i�H�j�Ôg |
| ���쐼�����n�k�i���d�R�����E���a��Ôg�j�P�V�V�P�N�O�S���Q�S�� |
| ���d�R�@�l8.0�i8.4�~2�j�A���n�k�B |
| �i���d�R�n�k�j���s���P�Q�O�O�O���ȏ�L���Q�A����Ôg�i�ő�30m�`80m�j |
| ���X�����n�k1763.01.29�@�l7.4�`8.0�@1968�̏\�����n�k�Ɏ����n�k�@���ҁE�s���s���@�Ôg�����B |
| ����i�n�k1707�i��i�S�N�j.10.28�@���{�E����C�@�l8.4�`8.7�@���{�j��ő�̋���n�k�̂P�B |
| ���s4,900�`25,000�A����80,000���A��Ôg�i15m�ȏ�j�A�L���k�B�A���n�k�B��i4�N |
| �����\�n�k�P�V�O�R�N�P�Q���R�P�����\��n�k�������Ă��܂��B��֓��@�l8.0�`8.2 |
| ���s����`10,000�A�]�˓��ʼnЖ҈ЁB�Ôg�A���N�ő�4m�A��֓��ő��̒n�k�B |
| �����k�����i�֏�`�[���j�P�U�V�V�N�P�P���S���@�@���̍��ڔ֏��Ђ̃y�[�W���Q�Ƃ��������B |
| �@���k�����i�֏�`�[���j�@�l8.0�@���s540�A�Ôg�B�Ôg�n�k�̉\��������B�֏�Ŕ�Q�G�l��330�˗����A��������A�����Ɣj���A�D97�z�A�j�����S75�l�A����l�����A���n30���i�����l�E�i��E���V��E����E�l�q�E�]�V��(�w�����\��N�`���N�֏�䗿���啗�J��g�^���V�ߊo���x�j |
| ���c���O���n�k���x�S�O�O�N�O�̂P�U�P�P�N�P�Q���Q���u�c���O���n�k�v�̑�n�k�������Ă��܂��B�u�������n�k���Ôg����B�v�ɒB�̓��ɂĒj���玵�S���\�O�l�A���n���\�ܓ��M�����B���A���݂̗����R�c���t�߁E�L�Z�����E��ƒ��E�Ìy�Α����ɂ���Q���� |
| ���k�����i�O���C�݁j�l8.1�@�A���n�k�B�@���s1,800�`5,000�A��Ôg�B��Òn������Q |
| ���c���n�k1605.02.03���{�E����C7.9�`8.1�i8.2�H�j |
| ���s2,500�`5,000�A�Ôg�B�����̐k���i���͘p�ł��n�k�H�j |
| ���������C�n�@���{�E����C1498�N9��20���@8.2�`8.4�i8.6�H�j |
| ���s16,000�`40,000�A��Ôg�B�l�����C�ƂȂ����B |
| ��������C�n�k�P�R�U�P�N�W���R���@�@��C�i�y���j�l8.2�`8.5 |
| �i���C�A���^�̋^�����j�������i�����H�j�A��Ôg�B |
| �����q�n�k1293.05.20���{�E��֓��l7.0�`7.5�i8�H�j���s����`23,000�i3���H�j�A�ЁB |
| ���N�a��C�n�k1099.02.22���{�E��C�i�y���j�l8.0�`8.3�@�L���Q�A�Ôg�B |
| ���i�����C�n�k1096.12.17���{�E���C�l8.0�`8.5�L���Q�A�Ôg�B |
| ���Ό��n�k�@�����O�N(1026�N6��17���A����5��23��)�̑�n�k�ɂ���l�ۏI���̒n�A�������C���ɖv�@�Ôg�����@�l�s�� |
| ���m�a�n�k�i�܋E�����n�k�j�W�W�V�N�W���Q�U�� |
| ����C�i�H�j�@�l8.0�`8.5�@�A���n�k�B |
| �������A��Ôg�A�L���Q�B���C�E��C�A���^�̒n�k�ƌ����Ă��邪�A�k���Ɉِ��i�����\�������j����B |
| ����1500�N�O���{�E��������i9�H�j����Ôg�@�A���n�k�B |
| �Ôg�E�n�k���N�̍��Ղ��琄���A ���C�E��C�E��B���ŘA������n�k���H1707�N��i�n�k�𗽂��K�͂̉\���B |
| �����P��C�n�k�U�W�S�N�P�P���Q�X���@��C�i�y���j�@�l8.2 |
| �L���Q�A�Ôg�B���E�ōł��Â�����n�k�L�^�̂P�B |
| ����ώO���n�k�W�U�X�N�V���P�R���͈͂́A�R�D�P�P�����{��k�ЂƓ����K�́H�@�A���n�k�B |
| ���k�����i�O���C�݁j�@�l8.3�`8.6(?)����ł́A�l9.0�̉\���� |
| ���s1,000�ȏ�i�������ӂ̐l���H�j�A�L�͂ɑ�Ôg�P���B�������ہB���Ƃ��Ȃ��B |
| 800�N����887�N�Ԃ̑�n�k�Ƒ啬�� | �u��Ղ����n�k�̗��j�v�|�Y�Z���@���숮���u������ |
| 800�N | �x�m�R�啬�� |
| 818�N�i�O�m9�N7���j | �֓���n�kM7.5�ȏ� |
| 827�N | ��������n�k |
| 830�N�i�V��7�N�j2��3�� | �H�c�������̒n�k |
| 850�N�i�Ï�3�N�j | �R�`���k�����̒n�k |
| 841�N�i���a8�N�j2��13�� | ���쌧�����̒n�k |
| 841�N�i���a8�N�j5��3�� | �ɓ��k���̒n�k�i�É��j |
| 850�N | �o�H��������n�k |
| 856�N | �������n�k |
| 863�N�i���5�N�j7��10�� | �z��E���z�n�k�i�V���j |
| 864�N | �x�m�R�啬��/937/1032/1083���̑����������Ă��܂��B |
| 868�N�i���10�N�j8��3�� | �d���n�k�i���Ɂj |
| 869�N�i���11�N�j7�N10�� | ���k���݂̋���n�k�@�n�k�ɔ����������ہB��������ϑ�n�kM8.3or8.4��������M9.0�������\�����B�����ɂ���Q��Â̒f�w�����B |
| 869�N�i���11�N�j12��14�� | ����n�k |
| 871�N | ���C�R���� |
| 878�N�i���c2�N9��29���j11��1�� | �֓��n�k�@M7.4�c���ґ����A���s�ޗǂŗL���v(���ȔN�\)�|�ɐ����f�w�i���˔����قg�o�Ƀ����N�j�|��ϒn�k�̗U�����H |
| 880�N�i���c4�N�j11��23�� | �o�_�n�k�i�����j�|�����f�w�| |
| 881�N | ��������n�k |
| 887�N�i�m�a3�N�j8��26�� | ��C����n�k�i���C�Ɠ����j�@�������m�a��n�kM8.0�`8.5 |
| �C�ے����\�̒n�k����̐��� �@�R�D�P�P�n�k��������A����l�i�b��l�j���l7.9�^�Ɣ��\�B���̌�b��l��8.3�^8.4�^8.8�ƏC���E�ύX���P�R���l9.0�ƕύX���܂����B �@�C�ے��̒n�k�\�m���̉��c�ے��͋L�҉�Łu�O�̋���ȁi�k����́j�j�A�T�����܂�̊ԂɘA�����Ĕ�������Ƃ����A���G�ȋN����������Ă���B�ɂ߂Ă܂�ŁA�C�ے��̊ϑ��ŏ��߂Ă̌o���v�Əq�ׂ��ƕ��Ă��܂����B�@�@�@�@�lj��Q�l�����X���P�P���L |
| �@��Ȓn�k�����ɂ���
�Q�O�P�P�N�R���̓��{����т��̎��ӈ�ɂ�����}�O�j�`���[�h�i�l�j�ʂ̒n�k�̔����͈ȉ��̂Ƃ���B
�Q�O�P�O�N�R���ȍ~�Q�O�P�P�N�Q�����܂ł̊ԁA��Ȓn�k�����Ƃ��ĕ]�����Ɏ��グ�����͎̂��̂��̂��������B
�R���X���ɎO�����Ń}�O�j�`���[�h�i�l�j�V�D�R�̒n�k���������A�{�錧�ōő�k�x�T����ϑ������B�܂��A��D�n�łT�T�����ȂǁA���k�n����k�C���n���E�֓��n���̈ꕔ�̑����m���݂���шɓ������ŒÔg���ϑ������B���@�R���X���ɎO�����łl�V�D�R�̒n�k�����������B���̒n�k�̔��k�@�\�͐��k���|���쓌�����Ɉ��͎������t�f�w�^�ŁA�����m�v���[�g�Ɨ��̃v���[�g�̋��E�Ŕ��������n�k�ł���B�f�o�r�ϑ����ʂɂ��ƁA���̒n�k�ɔ����A��D�n�ϑ��_�i��茧�j����R�������쓌�Ɉړ�����Ȃǂ̒n�k�ϓ����ϑ�����Ă��� |
| �Q���Q�Q���@�j���[�W�[�����h��N���C�X�g�`���[�`�łl�U�D�R�@���҂U�T�l�k���̐[���T�`�B �@�Q�O�P�P�N�Q���Q�Q���ߌ�O���T�P���i���{���ԓ��ߑO�W���T�P���j����A�l�U�D�R�̋����n�k�����B�P�R����ɂl�T�D�U�A�ߌ�Q���T�O������l�T�D�T�̗]�k�B�����̓��{�l����ЁB �@�Q���Q�Q���̒n�k�́A��N�X�����������l�V�D�O�̋����n�k�������B���̗]�k�Ƃ̎��B�X���̒n�k�̍ۂ́A�����Ȃǂɂ͑傫�Ȕ�Q���o�܂������A���҂͏o�܂���ł����B�@�@�@�@�Q���Q�R���t���u�Ԋ��v���X���P�P���}�� |
������w�g�o�n�k�������̂��
�Q�l�f�[�^�G�n�k�����m���ɂ���
�n�k�����m���@�@�@�@�@�@�@�@�@1995�N ��_�W�H��k�Ђ̏ꍇ
| �@�@�@�@�@�@�@���@�@���@�@�n�@�@�k | �@�@�n�k�������O�̂R�O�N�m�� | �@�@�f�w�̕��ϊ����Ԋu |
| 1995�N1��17�����Ɍ��암�n�k(M7.3)�Z�b�E�W�H���f�w�̏ꍇ | �@�@�@�@�@�@�@�@ 0.02%�`8% | �@�@�@�@�@�@�@��1.7�`3.5��N |
���̗\�����l�ł��A�_�ˁE�W�H�̑�k�Ђ��N����܂����B
|
�@�@�@�_ |
�������|�ݏ֖� | ���k���|������ | �����|��։� |
| 2011�N�����{ | �@ | �@ | �@�@�@�� |
| 1611�N�c���O�� | �@�@�� | �@ | �@ |
| 12�`13���I | �@ | �@�@�@�� | �@ |
| 869�N��� | �@ | �@ | �@�@�@�� |
| 2000�N�O | �@ | �@�@�@�� | �@ |
| 2500�N�O | �@�@�� | �@�@�@�@ | �@�@�@�@�� |
| 3000�N�O | �@ | �@�@�@�� | �@ |
| 3500�N�O | �@�@�� | �@ | �@�@�@�@�� |
| �����N | �l | �n�k�� | ���ҁE�s���s���� | �Ôg |
| 1872 | 7.1 | �l�c�n�k�i�������j | 550 | �� |
| 1891 | 8.0 | �Z���n�k�i�����j | 7,273 | �@ |
| 1894 | 7.0 | �����n�k�i�R�`���j | 726 | �@ |
| 1896 | 8.5 | �����O���n�k�i���E�{��j | 21,959 | �� |
| 1896 | 7.2 | ���H�n�k | 209 | �@ |
| 1923 | 7.9 | �֓��n�k | 105,000�] | �� |
| 1925 | 6.8 | �k�A�n�n�k | 428 | �@ |
| 1927 | 7.3 | �k�O��n�k | 2,825 | �� |
| 1930 | 7.3 | �k�ɓ��n�k | 272 | �@ |
| 1933 | 8.1 | ���a�O���n�k | 3,064 | �� |
| 1943 | 7.2 | ����n�k | 1,083 | �@ |
| 1944 | 7.9 | ����C�n�k | 1,223 | �� |
| 1945 | 6.8 | �O�͒n�k | 2,306 | �� |
| 1946 | 8.0 | ��C�n�k | 1,330 | �� |
| 1948 | 7.1 | ����n�k | 3,769 | �@ |
| 1968 | 7.9 | �\�����n�k | 52 | �� |
| 1978 | 7.4 | �{�錧���n�k | 28 | �� |
| 1983 | 7.7 | ���{�C�����n�k | 104 | �� |
| 1991 | �^ | �N�_��E�����x���E��ӗ� | 43�����S | �@ |
| 1993 | 7.8 | �k�C���쐼���n�k | 230 | �� |
| 1994 | 7.3 | �O���͂邩���n�k | 3 | �� |
| 1995 | 7.3 | ���Ɍ��암�n�k�@�W�H�E�_�� | 6,437 | �� |
| 2000 | 7.3 | ���搼���n�k | 0 | �@ |
| 2001 | 6.7 | �|�\�n�k | 2 | �@ |
| 2003 | 7.0 | �{�錧�k�����n�k | 0 | �� |
| 2003 | 8.0 | �\�����n�k | 2 | �� |
| 2004 | 6.8 | ���z�n�k | 68 | �@ |
| 2005 | 7.0 | ���������n�k | 1 | �@ |
| 2005 | 7.2 | 8.16�{��n�k | 0 | �� |
| 2007 | 6.7 | �\�o�����n�k | 1 | �� |
| 2007 | 6.8 | ���z���n�k | 15 | �� |
| 2008 | 7.2 | ���{������n�k | 17 | �@ |
| 2011 | 9.0 | ���k�n�������m���n�k | 20,458 | �� |
| 2011 | 7.1 | 4.11�n�k�i�]�k�j���m�x�f�w | 4�i�f�w�ɂ��j | �@ |

| �@���P�W�V�Q�N�Q���S���u�������l�c���n�k�v�̋L�^�@���������Z�S�v�蒬�o�g�i�����ɐ��܂ꖾ�������玖��S�A���Z�S�̐l�X��k�C���Ɉږ��������v�蒬�g�������o�g�̕ēc�a��i�v�菬�w�Z������j�́u�c�����s�^�v�i�k�C����w�E�k�������ٕۑ��j�ؑ����Y���� �@��1026�N�i�����R�N�j�U���P�V����n�k�E�^���i�Ôg�H�j�i�u�c�����s�^�v�ēc�a�꒘�A�y�ыv�蒬���v�j�E�N�\�|�v�蒬�j����@�n�ӌ��ޒ����o�T�j �@���Q�O�P�P�N�U���S���O�P���T�V���ɓ����������̐[���P�P�����łl�T�D�Q�̒n�k�i�ő�k�x�S�j�����������B���̒n�k�̔��k�@�\�͖k���|�쓌�����Ɉ��͎�����������f�w�^�ł������B���̒n�k�͒n�k���Ŕ��������B�ő�k�x�P�ȏ���ϑ�����]�k���T�����Ă���B �@�P�X�Q�R�N�W���ȍ~�̊���������ƁA����̒n�k�̐k�����ӂł́A�P�X�X�V�N�U���Q�T���ɎR�����k���łl�U�D�U�̒n�k�i�ő�k�x�T���j���A�Q�O�O�O�N�P�O���U���Ɂu�����P�Q�N�i�Q�O�O�O�N�j���挧�����n�k�v�i�l�V�D�R�A�ő�k�x�U���j���������Ă���B�i���̕����́A�C�ے����\���j�i��L�X���Q�T���}���j �@���u���t�ӂ����ܕ��ɇL�v�ɂ���2003�N���ΎR�ɂ��ĐV������`���s�Ȃ����Ə����Ă���܂��B����ɂ��ƁA���ΎR�Ƃ́w�T�ɉߋ�1���N�ȓ��ɕ������ΎR�A�y�ь��݊����ȕ��C�����̂���ΎR�x�̂��Ɖ]���B�i�ΎR���Η\�m�A����j�]���̒�`�́A�w�ߋ����悻2000�N�ȓ��ɕ������ΎR�y�ь��݊����ȕ��C�����̂���ΎR�x�Ƃ���Ă����B�V���Ɋ��ΎR�ɕI�܁E����i���k�j�E�j�Z�R�k�C���j�E�O�r�R�i�����n���@�������j�Ȃ�18�̎R�������108�̊��ΎR�̂��Ƃł��B�i�u���t�ӂ����ܕ��ɇL�v�o�T�@�lj��G7��7���j |
| ��ʋ@�ւ́A�卬���Ɋׂ���������̑�k�Ђœ����{�S���ŁA�V�������͂��ߍݗ����𑖂��Ă����ԗ��ɏ�Ԃ��Ă����l�A��l�̍ЊQ�҂��o���Ȃ��������Ƃ́A�^�����ׂ��ł��B�Ôg����v���ɔ����l�A�����U�������l�X�B |
�n�k�����������i�{���E�C�ے��E�h�ЉȊw�Z�p�������E���y�n���@�E������w�n�k�������E�Ɨ��@�l�y�،������E���{���f�w�w��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ЃN���A���A���
| �n�k�����������i�{�� | |||
| 2011�N4��11���������l�ʂ�̒n�k�Ɋւ����� | ||||
| �C�ے� | ||||
| �u����23�N�i2011�N�j���k���{�����m���n�k�ɂ��āi��35��j���S��pdf�� | ||||
| �h�ЉȊw�Z�p������ | ||||
| ���k�n�������m���n�k�ȍ~�̈�錧�k���E�����������̒n�k���� | ||||
| ���y�n���@ | ||||
| ����23�N�i2011�N�j3��15��22��31�����̒n�k�ɔ����n�k�ϓ��ɂ��� | ||||
| ������w�n�k������ | ||||
| 2011�N4��11���̕������l�ʂ�̒n�k�ɔ����n�\�n�k�f�w�ɂ��� | ||||
| �Ɨ��s���@�l�y�،����� | ||||
| 4��11���̗]�k�ł��킫�s�ɏo�������n�\�n�k�f�w�i����j | ||||
| ���{���f�w�w�� | ||||
| 2011�N4��11��17��16���ɔ��������������l�ʂ�̒n�k�iM7.0�j�Ɋւ����� | |||
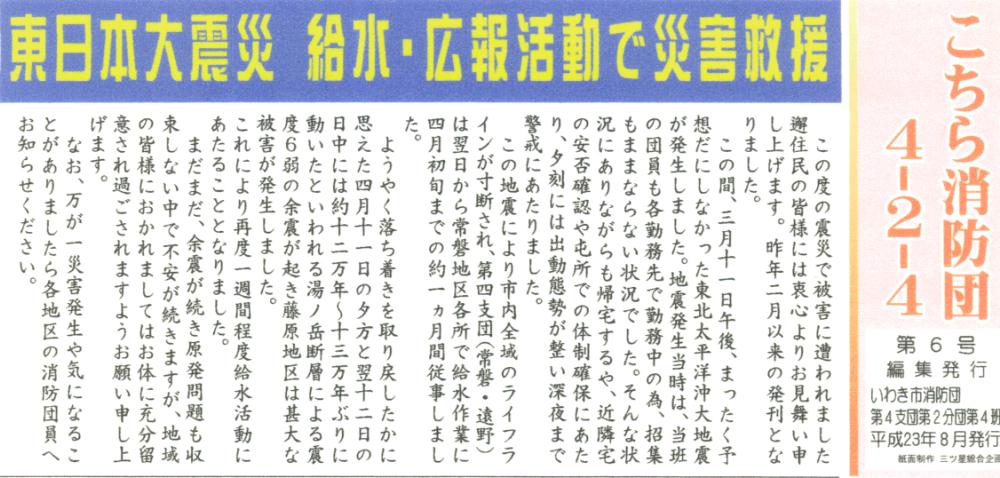 |
�Q�l�@�n�k�E�f�w�^�����֘A��HP
�g�c���ދL�O�������g�c���ނɂ��u��ϒn�k�v�Ɋւ���_���F����39�N12�����\�@�@
4.11/4.12�n�k�̐V�����Љ�܂��B
| �����d�͕�����ꌴ�q�͔��d�������ɔ������ː�����l�Ƒ���ꏊ�̒n�}�����m�x���a��������2011/7/25�ȍ~���葬��@�Q�l�G���{�̕��ϓI�Ȕ픚���ʂ́A0.04�`0.06��Sv/h�ƌ����Ă��܂��B |
�����d�͂Ɛ��{�̐ӔC�ŕ����������ׂĂɁA�ώZ���ː����ʌv���ŗ^����ׂ��ł��B�����v�����܂��B�I�܂��A�H�i�̕��ː��ʂ̑����v�]����A�S�Ă̈��H���̑�����ōs����Ԑ����I
| �Q�l�����G�����l�ɏP�������Ôg�N�\�ƌ����n����F�@�W�U�X�`�P�X�U�W�@�|�������ܕҏW���ł��| |
|
�O�k�^�{��k���@�k�x�T��@�l�V�D�R���E��D�n�`�ŒÔg�U�O�a�@ �@�R���X���ߑO�P�P���S�T������A���k�n���ŋ����n�k������A�{�錧�k���Ők�x�T��̂����ϑ����܂����B�C�ے��ɂ��ƁA�k���n�͎O�����ŁA�k���̐[���͖�W�`�A�n�k�̋K�́i�}�O�j�`���[�h���l�j�͂V�D�R�Ɛ��肳��܂��B�����͓͂��k�n���̑����m���ɒÔg���ӕ�߁B�ߌ�O���P�U����茧�E��D�n�`�łU�O�a�̒Ôg���ϑ��B���ӕ�͔��߂����R���Ԍ�ɉ�������܂����B �@�ߑO�P�P���T�V������ƌߌ�P���R�V������]�k�ƌ�����n�k������A���ꂼ��{�錧�ȂǂŐk�x�R���ϑ��B�C�ے��́A�ő�P�T�Ԃ͐k�x�S���x�̗]�k�������Ƃ��Ē��ӂ��Ăт����܂����B �@�Ôg�͂��̂ق��A�ߌ�O���Q�T���ɋ{�錧�Ί��s�̈���ŁA���P���P�R���Ɋ�茧�v���`�ł��ꂼ��T�O�a���ϑ����܂����B �@�C�ے��ɂ��ƁA����̒n�k�͐��k���|���쓌�����Ɉ��͂����������t�f�w�^�ŁA�����̃v���[�g�i��j�Ƒ����m�v���[�g�̋��E�ŋN���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Ԋ��v3��10���t����蔲�� ���̋L���́A�R�D�P�P�����{��k�Ђ̑O�k�ƁA�Ƃ炦�邱�Ƃ��o���܂��̂ŎQ�l�ɋL�ڂ������܂����B�R�D�P�P�̑�k�Ђ���������܂ł́A�����҂�w�҂̒��ɂ́A���̒n�k���{�k�ł���ƍl���Ă����l�����܂����B���؈��� |
| ���j �R���X���ɎO�����łl�V�D�R�̒n�k�i�ő�k�x�T��j�����������B�ߑO11��45�� �O���� M7.3 �k�x5�����̒n�k�̍ő�]�k���R���P�O���ɔ��������l�U�D�W�̒n�k�i�ő�k�x�S�j6��23�� �O���� M6.8 �k�x4�ł���B ���j �R���P�P���ɎO�����łl�X�D�O�̒n�k�i�ő�k�x�V�j�����������B�C�ے��͂��̒n�k���u�����Q�R�N�i�Q�O�P�P�N�j���k�n�������m���n�k�v�Ɩ��������B���̒n�k�̍ő�]�k�͓����ɔ��������l�V�D�V�̒n�k�i�ő�k�x�U��j�ł���i�S���W�����݁j�B ���j �R���P�P���ɕ��������ʂ�łl�T�D�P�̒n�k�i�ő�k�x�s���F�������j�����������B ���j �R���P�P���ɋ{�錧�암�łl�T�D�Q�̒n�k�i�ő�k�x�S�j�����������B ���j �R���P�Q���ɏH�c�����łl�U�D�S�̒n�k�i�ő�k�x�S�j�����������B �i��L�́A�����Q�R�N�S���P�P���n�k�����������i�{���n�k�����ψ���̎����ɂ��B�j |
| �C�ے��n�k���2011�N3��11�� 15��1�����\�Q�O�P�P�N�R���P�P���ߌ�Q���S�U���̑S���̐k�x���f�ڂ��Ă��܂��B |
2011�N3��11����
|
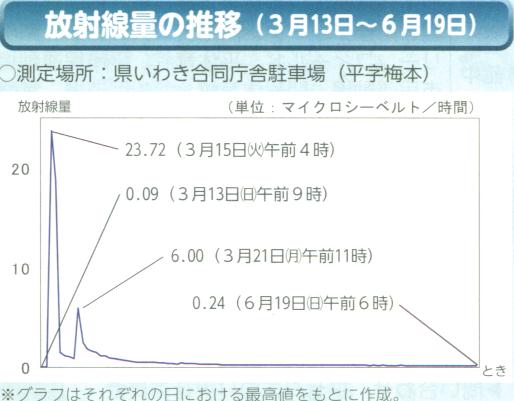 �O���t�ɕ\������Ɖ���₷���B����l�́A���̓s�x�A���\���Ă��炢�������̂��B�ǂ̂悤�ɂ���A�s���ɂ��̏�͂��̂��B�K�v�Ƃ��鎞�������̏�~�����̂��B�R�D�P�P�ȍ~�̏��́A�S������Ȃ��B�����e���r�Łu�z��O�̎��́v�A�u���������N�ւ̉e���͖����v�A���J��Ԃ������B |
| �@�E���̓��{�ɂ�����n�k�E�ΎR�̗���\�ɂ��� �@�u���{�̉Ȋw�ҁv2011.11�����n�k�ƌ������́|���������k�Ђ̓O�ꌟ���|���Ή돺����������p�Ƒ��؈��ňꕔ�lj� 1100�N�O�̒�ϒn�k�ł́A���s1,000�ȏ�A�L�͂ɑ�Ôg�����ݕ��P���B���n�ł����Պm�F�B��ؖk���܂ŁB�����̓��{�̐��v�l���ܕS���l�B�����̎x�z�ҁA�G���Ă����ڈ̐l�X�������u�ĂȂ��A�~�����邱�Ƃ𖽂��Ă���B�i�O����^����j ��ϒn�k�E�Ôg�̌����́A�����̐l�X�ɂ���Č������Ȃ���Ă��܂��B ��ϒn�k�ɂ��ĂW�U�X�N�i��ςP�P�N�j�T���Q�U�������̍��̋�����ԂЂǂ���Q�ɂ������B�}�O�j�`���[�h�W�D�T�i�k�x�U�j�Ɛ��肳��Ôg�̔g����͋{�錧�����錧�k���ɂ����Ĕ�����������n�k�ł������B�i���{��w�����w���f�W�^���A�[�J�C�u���j |
|
�@�������̑����m�������ł́A�����S��ɔ�Q���y�ڂ����P�X�R�W�N�̕������������n�k�i�l�V�D�T�j��P�X�W�V�N�ɕ��������ő����Ă��������������n�k�i�ő�l�U�D�V�A�l�U���x�̒n�k�͂T��j�Ȃǂ��m���Ă��܂����A�l�W���z����悤�ȋ���n�k�̔����͒m���Ă��܂���B�P�X�R�W�N�̕������������n�k�͉�����̓����Ŕ������A�����̍L���͈͂Ők�x�T���ϑ�����܂����B�����l�̌������ł͂P�O�V�����̒Ôg���ϑ�����܂������A�Ôg�ɂ���Q�͂���܂���ł����B�n�k�̗h��ɂ��Ɖ��A���H�A�S���Ȃǂ̔�Q���܂߁A�����Ŏ��҂P���Ȃǂ̔�Q�������܂����B���̒n�k�̗]�k�����͔��Ɋ����ł���A�{�k�̂Q���Ԍ�ɂl�V�D�R�A���̓��ɂ͂l�V�D�S�̗]�k����������ȂǁA�l�V���x�̗]�k�����ł���Q�����ԂɂU�����܂����B���̊C��ł́A����n�k���Ȃ������ɔ�r�I�傫�߂̒n�k�i�l�V���x�j����������X��������悤�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�n�k�����������i�{���̂g�o���@ |
| �@�N���� | �@���� | �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�@�@�@�@�@�� |
| 2011/3/9 | 11:45 | �O�k�����@�O����M7.3�@�i�ő�k�x�T��j�R���X���ɎO�����łl�V�D�R�̒n�k�i�ő�k�x�T��j�����������B�܂��A��D�n�łT�T�����ȂǁA���k�n����k�C���n���E�֓��n���̈ꕔ�̑����m���݂���шɓ������ŒÔg���ϑ������B |
| 2011/3/10 | 06:23 | �O�k�����@�l�U�D�W�̒n�k�i�ő�k�x�S�j |
| 2011/3/11 | 14:46 | �O�����Ń}�O�j�`���[�h�X�D�O�̒n�k�����@�P�`�R���@��������~�A�O���d���������B |
| 2011/3/11 | 14:50 | �C�ے���Ôg���ӕ� |
| 2011/3/11 | 15:14 | ���{�A�ً}�ЊQ���{����ݒu |
| 2011/3/11 | 15:15 | �k���̐[��80km�@M:7.4�@��錧�� �ő�k�x:�U�㔭�� |
| 2011/3/11 | 15:26 | ��Ôg���g�g���C�ݏP���i���킫����Ўʐ^�W�u���킫�̋L���v���j |
| 2011/3/11 | 15:35 | 21�b�ȏ�̑�Ôg���d��ꌴ�����P���B |
| 2011/3/11 | 15:41 | ���p�f�B�[�[�����d��̏��~�B�����d�́A��ꎟ�ً}���Ԑ��߁B |
| 2011/3/11 | 15:45 | �I�C���^���N����Ôg�ɂ�藬�o |
| 2011/3/11 | 15:50 | ���n�`�ߌ�3��50���|7m30cm�ȏ�̑�Ôg���ϑ��^��錧���`�ߌ�4��52���|4m20cm�Ôg���ϑ��^���`3��21���|4m20cm�̒Ôg���ϑ��^�{�Í`3��21���|4���ȏ�̒Ôg���ϑ�(NHK�ɂ��) |
| 2011/3/11 | 16.00 | �ۈ��@���p�d���i�f�B�[�[�����d�@�j�ߌ�S�����q�͍ЊQ���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��P�T��ʕ� |
| 2011/3/11 | 16:36 | �P���@�ƂQ���@�́A���p�F�S��p���u�ɂ�钍�����s�\�ɂȂ�B |
| 2011/3/11 | 17:41 | �k���̐[��30km�@M:5.8�@�������� �ő�k�x:�T�� ���� |
| 2011/3/11 | 19:03 | �}��K�j���[�������A�u���q�ً͋}���Ԑ錾�̔��߁v���L�҉ |
| 2011/3/11 | 19:35 | ���������k���̐[��80Km �l5.1���킫�k�x4 |
| 2011/3/11 | 20:50 | ���������{���́A�P���@�̔��a�Q�L���̏Z���P�W�U�S�l�ɔ��w�� |
| 2011/3/11 | 21:23 | ���t������b�A�P���@�̔��a�R�L���ȓ��̏Z�l�ɔ��߁A���a�R�L������P�O�L�������̏Z���ɑ������ҋ@�̎w�� |
| 2011/3/12 | 01:�� | �P���@�̊i�[�e��̈��͂��v�z��̂P�D�T�{�� |
| 2011/3/12 | 03:59 | �k���̐[��10km�@M:6.6�@�V�������z�n�� �ő�k�x:�U������ |
| 2011/3/12 | 04:32 | �k���̐[��10km�@M:5.8�@�V�������z�n�� �ő�k�x:�U�� ���� |
| 2011/3/12 | 05:42 | �k���̐[��0km�@M:5.3�@�V�������z�n�� �ő�k�x:�U�� ���� |
| 2011/3/12 | 06:�� | ���q�͈��S�E�ۈ��@�A�P�C�Q���@�̒������䎺�Œʏ�̂P�O�O�O�{�ɂ�����P�T�O�}�C�N���V�[�x���g�^�����ϑ��Ɣ��\�B |
| 2011/3/12 | 09:55 | �ۈ��@�A�P���@�̔R���_���ꕔ�I�o���A�핢�ǂ��n���n�߂Ă���\�����L��Ɣ��\�B |
| 2011/3/12 | 14:�� | �ۈ��@�A�P���@���ӂŃZ�V�E�������o�Ɣ��\�B |
| 2011/3/12 | 15:36 | �P���@�Ŕ����������A�����d�͂Ƌ��͉�Ђ̎Ј����S������ |
| 2011/3/12 | 20:20 | �P���@�ւ̊C���������J�n�B |
| 2011/3/12 | 21:�� | ���[�����́A���f�����ʼn��O�ɂ����R�l���픚�����Ɣ��\�B |
| 2011/3/13 | 02:44 | �R���@�i�R���@�ł́A2010�N9������v���T�[�}���^�]���j�ŗ�p���u����~�B |
| 2011/3/13 | 04:15 | �R���@�ŔR���_���I�o���n�߂�B |
| 2011/3/13 | 08:56 | ���ː��ʂ��Ăя㏸���A�����l�̂O�D�T�~���V�[�x���g�^�����z����B�������́A�픚�҂����킹�Čv�Q�Q�l���m�F�Ɣ��\�B |
| 2011/3/13 | 09:08 | �R���@�ɐ^���̒������J�n�B |
| 2011/3/13 | 09:20 | �R���@�̊i�[�e��̔r�C���J�n�B |
| 2011/3/13 | 12:55 | �R���@�R���_�̏㕔�P�D�X�b����p������I�o�B |
| 2011/3/13 | 13:12 | �R���@�̌��q�F�ɊC���̒������n�߂�B |
| 2011/3/13 | 13:52 | ������ꌴ���ł́A�ł������P�D�T�T�V�T�~���V�[�x���g�^���̕��ː��ʂ��ϑ� |
| 2011/3/13 | 18:00 | �C�ے��@�Ôg���ӕ�S�ĉ��� |
| 2011/3/14 | 11:01 | �R���@�̌����������A��ƈ��y�ю��q�������킹�ĂP�P�l���� |
| 2011/3/14 | 19:45 | �Q���@�̗�p�����啝�Ɍ������A�R���_�����ׂĘI�o�B |
| 2011/3/14 | 21:37 | ������ꌴ���̐���t�߂łR�D�P�R�O�~���V�[�x���g�^�����ϑ� |
| 2011/3/15 | 06:10 | �Q���@�̌����������@ |
| 2011/3/15 | 09:30 | �S���@�����̂S�K�������o���B |
| 2011/3/15 | 11:59 | ���y��ʏȂ͕�����ꌴ���̔��a�R�O�L���ȓ��̏������x�Ɋւ�炸��s���֎~�Ƃ���B |
| 2011/3/15 | 22:31 | �k���̐[��10km�@M:6.0�@�É������� �ő�k�x:�U������ |
| 2011/3/16 | 05:45 | �S���@�ōĂяo�� |
| 2011/3/16 | 08:37 | �R���@�Ŕ������オ���A�����C���o���Ɛ����B |
| 2011/3/17 | 09:48 | �R���@�ɁA���q���̃w���R�v�^�[�Q�@���v�S��R�O�g���̕����A���h�Ԃ�����Ԃł̕����n�܂�B�������ɑ��d�����������ލ�Ƃ��n�܂�B |
| 2011/3/18 | �@ | ���͗e����ɊC���𒍓��B |
| 2011/3/18 | �@ | ���킫�s���E�f�܂̔z�z���߂�B |
| 2011/3/19 | 10:�� | ���E�f�܂���������������Ă���B�����ɔz�z�B |
| 2011/3/19 | 16:07 | ���[�����́A���������̌����A��錧���̃z�E�����\�E����H�i�q���@��̎b���l���z������˔\�Z�x�����o�Ɣ��\�B |
| 2011/3/19 | 18:56 | �k���̐[��20km�@M:6.1�@��錧�k�� �ő�k�x:�T���̒n�k���� |
| 2011/3/22 | 18:20 | ���J�Ȃ́A�������̂T�s�����̐�������A�����̊�l���z������ː����E�f�����o�Ɣ��\�B |
| 2011/3/22 | �@ | ���d�A�T�[�x�C�}�b�v�i�~�n�����ː��ʃ}�b�v�j�̑���J�n�A����č��i�m�q�b�j�ɕi�������F�V��2012/2/12�t�����j |
| 2011/3/23 | 07:12 | 7.12M6.0 /7.13M5.8 /7.34M5.5 /7.36M5.8�A�� �l���n�k�����k������������킫�s�암 |
| 2011/3/23 | 18:55 | �[���@�k���̐[��10km�@M:4.7�@�������l�ʂ� �ő�k�x:�T�� ���� |
| 2011/3/23 | �@ | �����s�́A������̐���������P�L��������Q�P�O�x�N�����̕��ː����E�f�����o�Ɣ��\�B |
| 2011/3/23 | �@ | ���{���{�ASPEEDI(�ً}���v�����˔\�e���\���l�b�g���[�N�V�X�e���j�̈ꕔ�����߂Č��\����B |
| 2011/3/24 | �@ | �R���@�ō�ƈ��R�l���픚�A���ː���w�����������Ɉڑ��A���Q�l�������픚 |
| 2011/3/25 | ���� | ��p���Z�x�P���{�A�R�o���g�U�O�A���E�f�P�R�P�A�Z�V�E���P�R�Ȃnj��o |
| 2011/3/27 | �@ | �Q���@�^�[�r�������n���ɗ��܂���������P�O�O�O�~���V�[�x���g�^���ȏ�̕��ː��ʂ��v���B |
| 2011/3/28 | �@ | �~�n���̓y�납���v���g�j�E�������o�B |
| 2011/3/31 | �@ | ������ꌴ���P�`�U���@�S�Ĕp�F�ɂƌ����B�������݂͔����Əq�ׂ�B |
| 2011/4/01 | �@ | �L�쒬�s���@�\�̎�������킫�s�ɗv�� |
| 2011/4/01 | 19:49 | �k���̐[��10km�@M:5.1�@�H�c�������k�� �ő�k�x:�T���� |
| 2011/4/02 | 09:30 | �������A�R���N���[�g�ǂ̋T��C�ɗ��o���Ă���̂𓌓d���m�F�B |
| 2011/4/03 | �@ | �����J���Ȃƕ������́A�V�C�^�P�o���l�Y�_�Ƃɗv���B |
| 2011/4/04 | 19:�� | �����~�n���̒�Z�x���˔\���������C�ɕ��o�B |
| 2011/4/06 | �@ | �P���@�i�[�e����ցA���f������h�����ߒ��f�K�X�������J�n |
| 2011/4/07 | 23:32 | �k���̐[��40km�@M:7.4�@�{�錧�� �ő�k�x:�U���n�k���� |
| 2011/4/11 | 17:16 | �k���̐[��10km�@M:7.1�@�������l�ʂ� �ő�k�x:�U�� �����B���̒n�k�ʼn��m���f�w�����@������ꌴ�q�͔��d���ł́A1���@����3���@�̊O���d�����r�₵�ꎞ���������f���ꂽ���A��50����ɍĊJ���ꂽ�B�y�����ꂪ��������Ȃǂ���4�l�����S���A�����҂�10�l�o�����B�C�ے��n�k�Ôg�Ď��ۂ́A�u�n�k���m����6.3�b���17��16��22.2�b�ɋً}�n�k����i�x��j�\���܂����B�v����ɁA�u11��18��00�����݁A�ő�k�x5����ϑ�����]�k��2������Ȃǁi17��17�����̒n�k�œ��m�x�f�w�������H�AM6.0��17��26���AM5,6�j�A�����̗]�k���������Ă��܂��B�v�ƕ��Ă��܂��B �@���̒n�k�ɂ��P�R���N�Ԃ�Ɋ��������A�u���m�x�f�w�v���o�ώY�ƏȌ��q�͈��S�ψ���E�ۈ��@�́A�Z���ɂȂ��ď��߂ĔF�߂�Ƃ����Ԕ����Ԃ�B�����炱���A�u���m�x�f�w�v�A�u��ϒn�k�v��Nj����Ă��������̂ł��B�u��ϒn�k�v���ۈ��@�y�ѓ��d�́A�������Ă��܂����B |
| 2011/4/11 | 17:26 | M:5.6�@�k���̐[��0km�@�ő�k�x:�T�� |
| 2011/4/12 | 14:07 | �k���̐[��10km�@M:6.3�@�������l�ʂ� �ő�k�x:�U�㔭���@�����S���P�Q��14��07���ɔ��������n�k�ɂ����Ă��A�����҂�1�l�o�����B |
�����d�͕�����ꌴ�����̂̌o�ߊT�v �R���X������S���P�Q����
�Q�l�����^�R�D�P�P�֘A�V���G�X�|�j�`�V���g�o�j���[�X�̍�����
�@�@�@�@�@�@�X�|�j�`�V���@�w�u�P�O�O�O�N�ɂP�x�v�̗h��A��ϒn�k�ƍ����x
�\
�@�@�@�@�@�@�X�|�j�` Sponichi Annex �@�Љ�̂g�o����]�ڂX���P�P���}��
�k�C���E�����������錧���ɂ����Ă̑����m���݂łl�X�N���X�̋���n�k���A����܂őz�肳��Ă��Ȃ��������k�|���������܂ߎO����Ƃ���_�����A�k����C���������b����2012�N1��26�������̐�厏�w�Ȋw�x�i��g���X�j�Ɍf�ڂ���܂����B
�u��������h�c�S�|�Q�|�S�v�̍L��� 2011/7/31�}��
| ��1995�N��_�E�W�H��k�Вn�k�l7.3�@�W�H�f�w�@���S6,437�l�@�������ہB |
| �P�X�T�Q�N�J���`���b�J��n�k�l�X�D�O �P�X�T�V�N�A���h���A�m�t��n�k�l�X�D�P �P�X�U�O�N�`����n�k�l�X�D�T �P�X�U�S�N�A���X�J��n�k�l�X�D�Q �Q�O�O�S�N�P�Q���Q�U���C���h�l�V�A�X�}�g��������n�k�l�X�D�O���C���h�m��Ôg�@ �Q�O�O�W�N�T���P�Q�������l���n�k�l�W�D�O�@���ҍs���s���W���V��l�ȏ��i�k���ܗւ̔N�j �Q�O�P�O�N�`�������n�k�l�W�D�W |
���킫���ӂ̒f�w�Ɋւ���n�} ���m�x�f�w���͂��߂Ƃ��邢�킫�̒f�w�i���k��w���ȕ���j�摜���N�C�b�N���܂��Ɗg��̒n�}�ɂȂ�܂��B ���킫�l�ʂ�̒f�w�̒n�} ���{�̒f�w�̒n�} �f�w�n���}�@�������u���m�x�f�w�v�E�u���m���f�w�v�͐��f�w�ł��B �u���m�x�f�w�v�̎��ӂ̒n���} |
|
���p�� ���� syncline ���Ȃ����n�w�̒J�ɓ����镔�������w�A���ΒJ�@�n�w�̌��Ε��ɉ����Ĕ��B�����J�i�L�������j �w�� anticline ���Ȃ��Ĕg��̒悷�n�w�̕�̕����i�L�������j |
�u���f�w��n�k�̋��Ёv2008�N�m�g�j�X�y�V������������
2005�N���f��NHK�X�y�V�����u�C���h�m��Ôg�`�f���Ŕ��邻�̑S�e�v����A�N�C�b�N�g��
���̔N�T���P�Q���A�l�W�D�O�̒����E�l���n�k�������Ă��܂��B
| �@�@�@�n�k�����N���� | �O��̌o�ߔN�� | �n�k�̋K�� | |
| 1 | 1793�N2��17�� | �@�@�|�|�|�|�| | �l8.0�`8.4 |
| 2 | 1835�N7��20�� | �@�@�S�Q�D�S | �l7.3���x |
| 3 | 1861�N10��21�� | �@�@�Q�U�D�R | �l7.4���x |
| 4 | 1897�N2��20�� | �@�@�R�T�D�R | �l7.4 |
| 5 | 1938�N11��3�� | �@�@�R�X�D�V | �l7.4 |
| 6 | 1978�N6��12�� | �@�@�S�P�D�U | �l7.4 |
| 7 | �@�H | �@�H | �@�H |
�{�錧���n�k�̔����ƋN���肤��\��(NHK�T�C�G���XZERO 2012�N9��16�����f�y�ѓ��m�x���a���������ׂ���)
�l�V�ȏ�̏����̗\���́A�V�́H�}�[�N�̗��ł��B